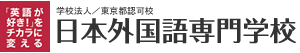REPORTER

佐賀県立佐賀西高校出身
アメリカ・カナダ留学コース2009年卒
ニューヨーク市立大学(4年制) バルークカレッジ 人材管理学専攻
2011年3月
専攻を変えて編入!
 大雪の翌日のミッドタウン
大雪の翌日のミッドタウン
さて、学校の方はというと、今学期からZicklin Business Schoolというバルークカレッジの中のビジネススクールに無事に入ることができ、2年ぶりにビジネス科目を取っています。待ちに待った専門分野の勉強も始まりました。
今学期一番楽しく、そして大変になりそうなのが専攻の選択科目である”Organization and Society”というクラスです。組織と社会の関わり方、最近どの企業も力を入れているCSR(企業の社会的責任)、そして経営者のモラルなどについて学んでいます。このクラスは20人という学生の少なさで、しかも主にディベートをするので本当に大変です。
他のクラスでもそんな環境の中で勉強しているせいか、今まで苦手だった「授業中に発言する」という行為が当たり前になってきて、むしろそれがないと退屈に感じるようにさえなりました。また、突然クラスの皆の前に立たされプレゼンの様なことをさせられても、あたふたしながらもジョークを交えつつこなせるようになったことに自分でも驚きました。
アメリカでの就職活動が本格的に!
 友達とリンカーンセンターでNYフィルのコンサートを聴きました。
友達とリンカーンセンターでNYフィルのコンサートを聴きました。
学校主催のインターンシップフェアにも、大手の金融機関や4大会計事務所を始め、多くの企業が参加しました。私も夏のインターンとして数社面接を受けてみましたが、見事に落されてしまいました。しかし、英語での本物の面接が経験でき、上達したつもりでいる自分の英語はまだまだだという事を思い知るいい機会になりました。
この就職活動を通して、バルークカレッジの強みをひしひしと感じています。ビジネス界で活躍している卒業生が多いため、学生主催のイベントにゲストとして訪れる先輩も、すごいキャリアを持っている人が沢山います。
そういう人たちの体験談、アドバイスからは新たなものの見方、リーダーになる人とはどういう人なのか、そして職に就いた後の自分の気持ちの持ち方の大切さなど、本当に色々なことを学べます。こんな機会は貴重だと思うので、できるだけ多くのイベントに足を運ぶようにしています。
今は夏休みの日本でのインターンシップを探している真っ最中で、JCFLの就職キャリアセンターの先生にも志望動機書を添削してもらい、大変お世話になっています。なんとかどこかでインターンシップができればいのですが…学業の傍らドキドキして落ち着かない日々が続いています。
小学校でのボランティア
 セントラルパークの木に雪で落書きがしてありました。
セントラルパークの木に雪で落書きがしてありました。
最初は、自分より英語が上手なアメリカ人の生徒に本を読むなんて…と不安だったのですが、始めてみれば子供はやっぱり可愛くて毎週一緒に楽しく読書ができるようになりました。 私が担当に振り分けられたのはご両親の仕事の都合でアメリカに暮らしている日本人の女の子(といっても英語で話します)で、将来は絵本作家になる夢を持っていていつも一生懸命読んでいます。私にもすごくなついてくれていて、クリスマスやバレンタインには手作りのカードをくれました。
時々他の生徒も担当するのですが、全員が読書に興味を持っているわけではないため、その子に合った方法で何とか本に興味を持ってもらうことが大変です。ほめたり、注意したり、教えたり…試行錯誤の繰り返しですが、必ずいつか役に立つと思うので毎週欠かさず参加しています。
2011年6月
NYの人々も日本を応援しています!
 震災の翌週学校で行われていた募金活動
震災の翌週学校で行われていた募金活動
私の学校では地震のあった3月11日の次の週からさっそく募金活動が始まりました。4日間の活動で1万1千ドル以上が集まったとのことです。私も慈善団体を通して街頭募金活動を行いました。多くの人が立ち止まりお金を入れてくれたり温かい言葉をかけてくれたりして、また、自分の生活も苦しいであろうホームレスの方までもがコインを入れてくれました。 人々の日本に対する気持ちを直に感じることのできた貴重な体験でした。
地震からしばらくたった今でもこちらでは様々な形で日本を支援する活動が行われています。アートを通じてお金を集めたり、日本文化を紹介するチャリティーイベントを行ったり…探せば毎日のようにどこかで何かイベントが行われています。ニューヨークの人々の気持ちがたくさん詰まったお金や作品が何かしらの形で被災地の方々に届けばいいなと願っています。
クラスメイトからも信頼してもらえるように!
 コンサートで行った教会
コンサートで行った教会
1年目はほとんどディスカッションはアメリカ人のチームメイト任せで、プレゼンテーションも自分の部分は簡単な部分を振り分けてもらったりしていました。3年目も終わりに近づいてきた今ではやっと、ここをこうしようと提案できるようになりましたし、人前でも堂々と話せるようになりました。
 春の休暇に仲のいい友達とAtlantic Cityに行ってきました。初めて見る大西洋をバックに記念撮影。
春の休暇に仲のいい友達とAtlantic Cityに行ってきました。初めて見る大西洋をバックに記念撮影。
苦手な教科の勉強などはまだまだ苦労することが多いし自分の出来なさ加減に落ち込むこともあります。しかしこうやってたまに自分のことを振り返ってみると、へこんだり喜んだりを繰り返しながら、ゆっくりでもしっかり学んでいるのだなと認識でき、また頑張ろうと思えます。
学外でも様々なことにチャレンジ
 ブルックリンの桜祭りで日本舞踊を披露しました。
ブルックリンの桜祭りで日本舞踊を披露しました。
奇しくもこのコンサートは元々仙台の合唱団との共演をするものでした。この地震の影響で多くの団員の方が渡米できる状態ではなくなってしまいましたが、チャリティーコンサートに形を変えて決行することになりました。プログラムには宮城県や岩手県の民謡もあるので、気持ちを込めて歌おうと思っています。
 セントラルパークの満開の桜
セントラルパークの満開の桜
これらの踊りはブルックリンの植物園で行われる「桜祭り」という大きなイベントで披露しました。着物が物珍しいのか、沢山の人に写真を撮られ、まるでミッキーマウスになったような気分でした 笑。
アメリカで日本の伝統に触れるのは中々楽しく、それを「異文化紹介」という形で人々に披露できるというのはとても嬉しいです。このように様々な経験や活動ができる機会が沢山あるのはニューヨークならではだと思います。
2011年11月
カーネギーホールの合唱コンサートに出演!
 カーネギーホールでのコンサートの日に一緒に出演した韓国人の友達と
カーネギーホールでのコンサートの日に一緒に出演した韓国人の友達と
私も一般公募でルームメイトと友人と共に参加しました。このコンサートには仙台の合唱団が参加し、総勢200名超で日本とアメリカの曲を10曲ほど披露しました。また、東海岸では有名なアメリカの男声合唱団とも共演し、日本とアメリカが音楽で通じ合った一夜となりました。大きな会場は大勢の観客で埋め尽くされ、最後はスタンディングオベーションで大成功のうちに幕を閉じました。
会場では募金活動も行われており、集まった募金は仙台の合唱団の方々が直接被災地に届けられたそうです。いつもは客席から見ているだけだったカーネギーホールでまさかステージでパフォーマンスできる日がくるなんて夢にも思っていなかったので大感激!初めは足が震えていましたが、とても楽しく歌うことができ、一生の思い出になりました。
より実世界で役立つ勉強へ
 アメリカ国旗の色にライトアップされたエンパイアステートビル
アメリカ国旗の色にライトアップされたエンパイアステートビル
授業時間の半分ぐらいはグループディスカッションで、その日学んだトピックを自分たちの職場環境、上司、同僚にあてはめて理解を深めます。
 ハロウィン用の大きなカボチャ
ハロウィン用の大きなカボチャ
教科書やレクチャーだけでは現実としてつかめない概念やモデルも、このように現実に当てはめて考えていけるので分かりやすくてとても好きなクラスです。このクラスも含め、教科書はいわゆる「教科書」に加え、実際のビジネスパーソンが読むような新聞のコラム集のようなものを使っています。
学部での勉強とはいえ、アッパークラス(上の学年)になればなるほど教科書だけにとどまらない、実際の世界で役に立つような知識を教えてくれている授業が多いという印象を強く受けています。
留学をして分かるマイノリティへの理解
 夜のタイムズスクエアで
夜のタイムズスクエアで
日本にいた頃はゲイの友達なんて一人もいなかったし、遠い世界のことのように感じていましたが、今は身近な友達にゲイの人もいます。 日本にいた頃は、「あの芸能人はゲイなんだって」「うそ、やだ~」というような会話をしていた覚えがありますが、今はそのようには思えなくなりました。同性愛者差別に限らず人種差別や民族差別、宗教差別など、どんな差別にも当てはまることだと思うのですが、その差別されているグループに属している人と実際に接して、話を聞くとそれまでとは全く別の思いが生まれると思います。
だから、差別や異文化間のいがみあいなどをなくすには、まずは直に交流を持ち、理解を深めることが大切なのだと思います。その意味では留学というのは最高の機会だし、世界中の人々と関わる素晴らしい経験になると思います。