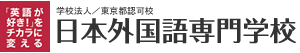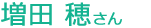2013年1月
国際政治を学ぶ上で興味深い「セルビア」へ!
みなさんこんにちは増田です!突然ですがみなさんはセルビアという国をご存知ですか?ギリシャの北にある小さな国です。実はこのセルビアという国が、国際政治を勉強する中で非常に興味深い国でして…。「気になるならとりあえず行ってみよう!」ということで、夏休みの最後に5日ほど1人で旅行に行ってきました。今回はイギリスのお話ではなくなってしまうのですが、私が大学で勉強していることの説明も踏まえて、セルビアレポートをさせていただきます。
90年代の「軍事的人道介入」が興味をもったきっかけ!
 内戦があったことを忘れさせる美しい景色
内戦があったことを忘れさせる美しい景色
その内戦の中で、「虐殺が行われている」という情報が入ったことで、国際社会はセルビアを空爆しました。このセルビアへの軍事介入は「危険にさらされている人たちを助けよう!」「悪いことをしているセルビアを懲らしめよう!」という「正義」の名目のもとで行われたのですが、結果的に多くの死傷者や難民を出すことになったことや、内戦の情報がかなり偏って報道されていたことなどがあって、国際政治学の中で絶えずその倫理性が問われている問題です。
私が特に興味を持った「プロパガンダ」とは?
私が特別ユーゴのケースに興味を持ったのは、介入をするかしないかで西欧諸国の立場が煮え切らない時に行われた、「プロパガンダ」がとても有効だったからです。「プロパガンダ」とは、一般に「政治的な目的に達するために行われる広報活動」のことを言います。本来ユーゴは政治的にもあまり重要な地域ではなく、西欧諸国にとって、人員や国家予算を割いてまで助けに行こうとするほどの重要な国でもありませんでした。ところが、とても効果的に虐殺の悲惨さを伝えるプロパガンダが行われたことで、世論や乗り気ではなかった政治家たちに「こんなにひどいことが起こっているのならば何かしなければ」と思わせることに成功し、最終的には軍事介入が起こりました。
もちろん、これ自体が良いことだったのか悪いことだったのかは、大きく評価が分かれます。ですが、私個人としては、何よりもそうやって広告活動の方法一つで、それまでの立場が大きく変わってしまうという、メディアの力の大きさに驚きました。以来私は1990年代のユーゴの内戦と、それに対する西欧諸国の軍事介入に特に力を入れて勉強しています。
もちろん、これ自体が良いことだったのか悪いことだったのかは、大きく評価が分かれます。ですが、私個人としては、何よりもそうやって広告活動の方法一つで、それまでの立場が大きく変わってしまうという、メディアの力の大きさに驚きました。以来私は1990年代のユーゴの内戦と、それに対する西欧諸国の軍事介入に特に力を入れて勉強しています。
内戦を乗り越え、前向きに生きる人々に触れて…

「戦争」というと「特別なこと」、というようなイメージがあったのですが、セルビアの人たちを見ていたら、そんなイメージが一新されました。もちろん彼らの中には空爆の苦い経験があるのでしょうが、だからといって社会が「戦争」の記憶だけに支配されているわけじゃない。当たり前のことなのかもしれませんが、毎日毎日戦争のことばかりを勉強している国際政治学部の学生としては、はっとさせられるものがありました。
セルビアの人たちとの交流も!
セルビアでは宿泊先が相部屋だったので、同じように旅行中の仲間とお互いのことやセルビアのことについて話したり、受付の女性とも仲良くなって、セルビアのことをいろいろ教えてもらったりしました。天気も良かったので、一人で公園で日向ぼっこしたり(イギリスは天気が悪いので、夏休み中にお日様に当たり溜めしておきました!笑)、お土産を売っているおばさんとカタコトのセルビア語で会話をしてみたり(実は最近独学でセルビア語の勉強を始めました)…、やっぱり興味を持ってチャンスがあるなら、いろんな国に行ってみると楽しいですね!
卒業論文はもちろん「ユーゴに対して行われた人道介入」!
10月の頭からは最終学年になり、最近は卒業論文に向けて動き出したところです。テーマはもちろん、「ユーゴに対して行われた人道介入」です。12,000単語というかなり大きな課題になりますが、自分の好きなこと、興味があることのプロフェッショナルへの第一歩、そして、JCFL時代から目指して努力してきたことの一つの集大成になると思うと、不安と同時にわくわくもします。1年間かなり忙しくなりそうですが、悔いの残らないラスト1年にしたいですね。
2013年2月
留学生活サバイバルの最重要ポイント!試験を乗り切る方法は?
 クリスマスの写真です。田舎なのであまり派手な装飾はありません(笑)
クリスマスの写真です。田舎なのであまり派手な装飾はありません(笑)
一概に期末試験といっても、学部や科目によってかなりタイプに違いがあります。わたしの所属する国際政治学部では基本的に「ショートアンサー(定義問題:「何々について説明しなさい」というタイプ)」と「ロングアンサー(小論文問題:「何々について意見を述べなさい」)」の2つのタイプですが、理系はもちろんビジネス系の学部では計算問題なども出るそうです。対策の仕方も変わってくると思うので、あくまで参考程度に考えてください。
重要なポイント、必要なことを的確に押さえる!
言葉のハンデがある中での試験で1番のポイントは、重要なポイントを的確に押さえること!予習でも試験の解答でもとにかくこれが基本になります。英語がネイティブでないと、勉強するのにも解答するのにも時間がかかるので、要点だけ抑えて確実に点を取りに行く戦法です。
1. 先生の話をよく聞くこと
基本なのですが、これがなにより重要(そしてけっこう見落としがち)。試験問題の説明をするときなど、どのトピックをやっておくといいか、どんな形式の問題が何問出るかなど説明してくれるので、しっかり把握しておきましょう。「ショートアンサー」なのか「ロングアンサー」なのか、それぞれ何問でるのか…それによって復習でどのくらい掘り下げて勉強しなくてはならないのかも決まります。
2.確実に出そうなトピックを重点的に勉強
一連の講義の中で、先生が特に力を入れていたトピック、過去にテストに出ていて重要そうなトピックなど判断します。「確実に出そうなトピックを考える」ことは、意外と時間がかかりますが、ここでしっかり的を決めて、そこに集中して勉強できるようにすることで、限りある時間を有効に使えるようにします。
1. 先生の話をよく聞くこと
基本なのですが、これがなにより重要(そしてけっこう見落としがち)。試験問題の説明をするときなど、どのトピックをやっておくといいか、どんな形式の問題が何問出るかなど説明してくれるので、しっかり把握しておきましょう。「ショートアンサー」なのか「ロングアンサー」なのか、それぞれ何問でるのか…それによって復習でどのくらい掘り下げて勉強しなくてはならないのかも決まります。
2.確実に出そうなトピックを重点的に勉強
一連の講義の中で、先生が特に力を入れていたトピック、過去にテストに出ていて重要そうなトピックなど判断します。「確実に出そうなトピックを考える」ことは、意外と時間がかかりますが、ここでしっかり的を決めて、そこに集中して勉強できるようにすることで、限りある時間を有効に使えるようにします。
 アベリストウィスにはウェールズの国立図書館があります。イギリスで出版された本はほとんどある、という蔵書量でキャンパスのすぐ隣にあるので試験や課題で大学にない本が必要な時はこっちに行きます。
アベリストウィスにはウェールズの国立図書館があります。イギリスで出版された本はほとんどある、という蔵書量でキャンパスのすぐ隣にあるので試験や課題で大学にない本が必要な時はこっちに行きます。
トピックを決めたらそれに関連する講義の復習をします。講義では先生が特に重要だと思っていることを言っているので、試験で解答しなくてはならない最重要ポイントの大枠はこれでつかみます。授業中にはそのトピックの中での問題などを提起してくれることもあり、そういったものは小論文問題になることもあるので把握しておくといいでしょう。ちなみに、わたしは先生に許可を取って、授業をボイスレコーダーに録音させてもらっているので、その回の講義をもう1度聞きなおします。講義中にノートは取っていますが、聞き逃してしまうことも多いので…。リスニングに不安のある方にはいい方法だと思いますよ!
4.リーディング
トピックに関するポイントの大枠をつかんだら、それを深めるように関連文献を読んでポイントを絞ります。講義の元になっている文献がシラバス(授業計画や課題、文献など、講義に関わるさまざまな事柄が書かれているもの)に書いてあるので、その中で特に重要そうなものいくつか読みます。わたしの場合「ロングアンサー」1問の予習につき文献2~3が最大、「ショートアンサー」の場合は講義のポイントだけ絞って文献は読まない場合もあります。
5.問題の予測~解答の練習
ある程度そのトピックのポイントを絞ったら、自分で問題を想定してみます。授業中の先生の問題提起や、過去問でどんな問題が出てきているのか調べて、それまで勉強してきたポイントを使ってどう答えるか試してみます。何度か試験時間と同じ制限時間を設けて、自分で模擬試験をしてみるのもいいですね。わたしはある程度問題を想定して、それに答えるようにポイントを書きだして覚えたりします。予想通りの問題が出た場合、何をどう答えるか考える時間が省ける分、書くこと自体に集中できるので、スペルや文法の間違いがないように確実に書いていくことができます。実際過去には何度か予想した通りの問題が出たこともあって、その時は「よっしゃあああ!」って感じでしたね(笑)
言葉のハンデがある分、復習することにも、ポイントを覚えることにも、試験中それを書きだすことにも人より時間がかかります。ですから的を絞って、確実に最低限、必要なことを抑えていくことがとにかく重要です。「ショートアンサー」のためにリーディングをしないのも、どの道自分のライティングのスピードでは、時間内に書ききれないためなんですね。というのも、わたしは以前にポイントを多く出し過ぎて、結局時間がなくて後半の重要ポイントを書ききれなかった、という苦い経験があります。重要なのは、自分の書ける量の範囲内で、ポイントに優先順位をつけて書いていくこと。書ききれない量の情報を得るために文献を読んだり理解したりするよりは、その分の時間を使って実際に問題想定して答えてみる練習をした方がずっと役に立ちます。
トピックに関するポイントの大枠をつかんだら、それを深めるように関連文献を読んでポイントを絞ります。講義の元になっている文献がシラバス(授業計画や課題、文献など、講義に関わるさまざまな事柄が書かれているもの)に書いてあるので、その中で特に重要そうなものいくつか読みます。わたしの場合「ロングアンサー」1問の予習につき文献2~3が最大、「ショートアンサー」の場合は講義のポイントだけ絞って文献は読まない場合もあります。
5.問題の予測~解答の練習
ある程度そのトピックのポイントを絞ったら、自分で問題を想定してみます。授業中の先生の問題提起や、過去問でどんな問題が出てきているのか調べて、それまで勉強してきたポイントを使ってどう答えるか試してみます。何度か試験時間と同じ制限時間を設けて、自分で模擬試験をしてみるのもいいですね。わたしはある程度問題を想定して、それに答えるようにポイントを書きだして覚えたりします。予想通りの問題が出た場合、何をどう答えるか考える時間が省ける分、書くこと自体に集中できるので、スペルや文法の間違いがないように確実に書いていくことができます。実際過去には何度か予想した通りの問題が出たこともあって、その時は「よっしゃあああ!」って感じでしたね(笑)
言葉のハンデがある分、復習することにも、ポイントを覚えることにも、試験中それを書きだすことにも人より時間がかかります。ですから的を絞って、確実に最低限、必要なことを抑えていくことがとにかく重要です。「ショートアンサー」のためにリーディングをしないのも、どの道自分のライティングのスピードでは、時間内に書ききれないためなんですね。というのも、わたしは以前にポイントを多く出し過ぎて、結局時間がなくて後半の重要ポイントを書ききれなかった、という苦い経験があります。重要なのは、自分の書ける量の範囲内で、ポイントに優先順位をつけて書いていくこと。書ききれない量の情報を得るために文献を読んだり理解したりするよりは、その分の時間を使って実際に問題想定して答えてみる練習をした方がずっと役に立ちます。
日本にいる間に自分の勉強スタイルを見つける!
 晴れてる日の国立図書館からの眺めです。
晴れてる日の国立図書館からの眺めです。
と、まあわかりきったようなことをつらつらと書いた気もしますが…。わたしはイギリスに来るまであまりこういうことを意識的にやっていなかったので、意識するきっかけになったらいいんじゃないかな?と思ってレポートさせていただきました。英語で勉強をしていると何をするにも時間がかかるので、無鉄砲にはやれません。試験対策に限らず課題や授業の予習など、優先順位をつけてやっていかないと、限られた時間内でこなし切れないので、無駄なことはしないように気をつけています。 こちらは後期が始まったばかりでしばらくは試験がありませんが、4月中旬の卒論の提出に向けて早速始動しています。通常の授業も今期は「サイバー戦争」と「国家設計」の授業を選択していて、他にもいくつか興味のある科目の聴講に行こうと思っているので、忙しくなる予感です。イギリスでの大学生活最後の学期、後悔のないようにひとつひとつ確実にこなしていきたいですね!
2013年7月
イギリスの病院事情をレポートします!
 家の隣はすぐ牧草地という田舎です。
家の隣はすぐ牧草地という田舎です。
外国語で病院に行くのは結構勇気のいるもので、3年こちらに滞在していますが実は今回で3回目の受診です。ロンドンなどの都市部には日系の病院もあるので、不安ならそちらに行くという手もありますが、ここは遥か西方ウェールズのド田舎。当然病院と言ったら現地の医者なります。と、いうわけで今回はイギリス病院事情レポートです。
国営の病院なら診療も処方薬も無料!
イギリスには国営の病院とプライベート(私立)の病院があります。プライベートは国営に比べると予約が取りやすく、診察を受けやすいことが強みのようですが、費用が全額患者負担になります。対して国営は待ち時間こそ長くなりますが、診察、処方薬は基本的に無料で提供されます。風邪の問診はもちろん、血液検査、わたしは日本で受けられなかった予防接種をイギリスに来てから国営の病院で打ったのですがそれも無料でした。未だに診察を受けて、そのままお金を支払わずに帰るというのには慣れませんが…(笑)。日系の病院はプライベートに含まれるのですが、わたしはもっぱら国営の現地病院に行っているので(といっても3回ですが…)なので、今回のレポートもそちらの説明になります。
まずは「NHS」に登録!
国営の医療機関にかかるには、病院で国営の保健サービス(NHS)に登録しておく必要があります。(登録はインターネットでもできるようですが、わたしは直接病院までいって登録しました。)6ヵ月以上の滞在だと外国人でも無料で登録できるので、それ以上の滞在であれば留学生でもOKです。NHSへの登録が済んでいないと、よほど重病でない限り病院に行ってもすぐ診察してもらえないので、現地に着いたらなるべく早く登録を済ませておくことをお勧めします。NHSの医療はまずは登録した病院でしか受けられないので(その後病状によっては専門医のいる病院に紹介してもらえるそうです)、大学の留学生受け入れセンターなどがあれば、そこで近場の信頼できる病院などを教えてもらうといいかと思います。
国営の病院は長時間待つ…(涙)。粘り強さと交渉で診察してもらったことも!
 わたしがお世話になっている病院。昨年建物を改装したので中はピカピカです。
わたしがお世話になっている病院。昨年建物を改装したので中はピカピカです。
ただ意外と、しつこく粘れば当日診てもらえたりもします(笑)。わたしの住む街は田舎で人口も少ないので患者の数に比較的余裕があったのかもしれませんが、「キャンセルあるかもしれないんでしょ?待合室で待ってちゃだめ?今日診てもらわないと困るの!」といってどうにか当日に診てもらった経験があります。イギリスでは「無理」と言われても実は「無理じゃない」ことが結構あるので、必要なら粘ってみるといいと思います。もちろんそれでもダメなときはありますが、わたしの経験では8割は「無理」と言われたことが覆ってます(笑)
「病院っぽさ」を感じないイギリスの病院。
他にわたしが感じるイギリスの病院と日本の病院の大きな違いは、イギリスのお医者さんはあまり「医者」っぽくないところ…でしょうか。イギリス以外でドイツでも何回か医者にかかったことがあるのですが、みんな白衣も着ていないし場合によってはジーンズにワイシャツ…なんてことも…。受付のおねえさんたちも普段着。診察室も医療器具こそ置いてあるけれど壁もカラフルで花が飾ってあったりして、診察室というよりは普通の事務室という感じ。その上診察も薬も無料…ということで、内心どーーも不安になってしまうんですよね、「本当にここは病院なの…?大丈夫なの…?」って(笑)
わたしは最初何も知らずにこちらで病院に行って、とても驚いて動揺したので(38度の熱でフラフラしながら慣れない海外でひとり病院に行ったら、病院が全然病院みたいじゃなかった時の不安感は相当のものでした。)、心づもりをしておくことをお勧めします(笑)。NHSの説明はJCFLでもあると思いますし、外務省のホームページにも詳しい説明が載っているようなので参考にしてみてください。
わたしは最初何も知らずにこちらで病院に行って、とても驚いて動揺したので(38度の熱でフラフラしながら慣れない海外でひとり病院に行ったら、病院が全然病院みたいじゃなかった時の不安感は相当のものでした。)、心づもりをしておくことをお勧めします(笑)。NHSの説明はJCFLでもあると思いますし、外務省のホームページにも詳しい説明が載っているようなので参考にしてみてください。
卒論も完成!あとは期末試験を残すのみ!!
 卒論終了しましたー!
卒論終了しましたー!
問題点もかなり残りましたがその辺は今後、大学院での研究で解決していければ、と思っています。とはいえまずは期末試験なので(苦笑)、残り2週間きっちり勉強して、気持ちよく7月の卒業式を迎えられればと思います。