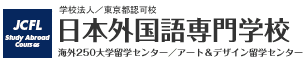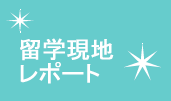ブリスベンはすっかり春になり人工の「Street Beach」は沢山の人で賑わうようになりました。今回は学校の授業のことや私自身の英語の上達具合について書きたいと思います。
大学院の授業
私は現在大学院で勉強をしているので、内容はとても専門的です。専攻はビジネスで、ビジネスは留学生にとって一番理解しやすい専攻の一つ言われていますが、それでも授業についていくのはとても大変です。やはりオーストラリア人や英語の環境で大学などの教育を受けた学生に比べると、かなり英語の理解力に差を感じます。現在専攻している科目は法律、会計と、日本語の直訳がありませんが「グローバリゼーション」という科目です。前の学期に勉強していたマーケティングやITビジネスの科目と比べると、はるかに大変です。
法律は、母国語でも理解しにくいものを外国語で勉強するので、理解にとても時間がかかります。授業中やチュートリアルの時間に、授業中にやった内容をもとにペアになって事例を分析して、どのような法的解釈ができるか、つまりどういった違反を犯したか、どういった罰になるか、またどうしたら防げるかの対策などについて話し合い、最後に発表します。授業自体の進み具合は早くありませんが、素早い理解力と表現力が求められます。
会計は、最初の数回の授業はとても早く感じました。この科目を受講している学生のほとんどは大学の学部で会計を学んできていて、また授業もある程度会計の知識があるものとして授業が進められているので、最初の数週間は全く授業についていけませんでした。会計の基礎を同じ時期に学んでいたJCFLからの友達がいたので、彼女に教えてもらい、その後はほぼついていけるようになりました。会計は数学的要素が強いので得意不得意がはっきりしますが、私は数学が得意なので問題なくついていけています。
最後にグローバリゼーションについてですが、このグローバリゼーションは日本語に無理やり訳すと(経済などの)地球規模化となることがあります。これは会社やビジネスについての科目ではなく、会社を取り囲む外部に関する科目で、先生が言うにはもっとも大学院らしい科目です。決まった教科書も無く、授業用の資料だけで授業が進められていくため、授業の内容より詳しく知りたい事が出てきたら、インターネットや図書館で個々に探さなければなりません。
最も苦労した事はエッセイを書くことでした。この科目のエッセイは決まったテーマが無く、個人個人がこの科目に関することで興味のあることを選び、先生と相談してテーマを決めて書くというもので、テーマを決めるのも一苦労でした。ちなみに私のテーマは日本経済における東アジア共通通貨の見通しについてでした。他の人も、世界の貧困問題、サーズの航空業界への影響、アジア通貨危機など様々なテーマで書いていました。私のテーマは将来の見通しで、自分の意見が中心なっていて一見好きに書けて良さそうですが、エッセイの中で自分の意見を述べるたびに、本やインターネットからその意見を支持する記事を探して、サポートしないといけないので、非常に時間がかかりました。また、細かい採点基準がなく、出版できる様なものが書けているかどうかが基準になるとだけ聞かされました。さらに、提出したあとにそのエッセイについて先生と面接を行い、そのエッセイについての質問をされました。まるで日本の大学の時に行った卒業研究や卒業論文のようでした。
英語の上達
英語は確実に上達している感じはします。最初の1〜2ヶ月はSpeaking、Listeningが伸びていくのが感じられました。授業は最初全く理解できませんでしたが、2ヵ月後にはかなり理解できるようになりました。しかし、その後はピタッととまった感じです。その一方で、Writing、Readingが3ヶ月目以降からどんどん伸びている感じがします。最初の学期はエッセイの点数はクラスで最下位に近いものでしたが、最近は平均点を下回ることはなくなりました。採点の仕組みが分かったというのもありますが、Writingの力も上がっているはずです。
Readingもかなりスピードが上がり、辞書を使わなくても、分からない単語の意味を推測しながら、文章を読めるようになりました。Writingは大学で勉強する上で最も大事な力だと感じています。英語の上達が手にとって分かるのでとても嬉しく感じますし、やりがいにもなっています。
かなり英語の能力は上がりましたが、それでもSpeaking、Listeningは、周りのクラスメイトと比べるとひどいものです。私の知る限り一人を除いて全員英語圏の大学を卒業していて、留学生でもさほど英語では苦労していないように見受けられます。その一人と私がダントツで英語力がありません。ただ、その彼は1年間ブリスベンで英語を勉強していたのに、その彼に追いつけたのはJCFLのおかげでしょうか。現地のそれぞれの訛りに慣れるのは少し時間がかかりますが、どの国で勉強しようと上達できます。どちらにせよ、留学してからも英語力を改善し続けていかなければなりません。
オーストラリアの病院
1ヶ月ほど前、野球で足を怪我して病院にいった話をします。オーストラリアでは怪我や病気の時はまずGPと言われる小さな診療所に行きます。あちらこちらにあります。日本のように内科、外科などと別れていません。まずGPに行って診察を受けました。そして、レントゲンを撮ることになりましたが、それには専門医に行かなければなりません。専門医に向かいましたが、ほとんど歩けなかったので、タクシーを使いました。レントゲンを撮ってもらったら、今度はフィルムをもってさっきのGPに戻ります。レントゲンをもとに再度診察を受けました。かなり丁寧に説明してもらいましたが、専門用語が飛び交っていて、「靭帯とアキレス腱がとても悪い」ということと、「10日くらい患部をバンテージで固定して、松葉杖を使いなさい」くらいしか理解できませんでした。次に向かった先は薬局です。薬局でバンテージを買って再びGPに戻ります。ここでバンテージの巻き方を習い、これでようやくGPとはお別れです。しかし、さっき行った薬局で松葉杖を借りることができなかったので、別の薬局に行き松葉杖を借り、ようやく終了です。かなり時間とお金を無駄にしました。オーストラリアの医療システムはかなり議論を呼んでいますが、私はとても嫌いです。