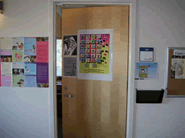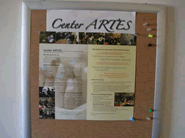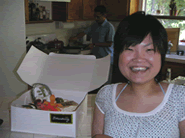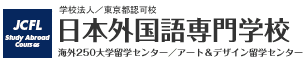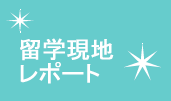No.4
「英語上達法」
「もうちょっと待って!」 「おなかすいた!」 これってスペイン語の音でどういう意味になるかご存知ですか?「もうちょっと待って」はmuchos totamoesでたくさんのトマト。「おなかすいた」はuna casitaで家を意味します。サンディエゴはメキシコとの国境の街でもあります。クラスの3分の1がメキシコ系の生徒であるなんてこともしばしば。アメリカ人でも大体基本のスペイン語は理解できます。なのでこれは私にとっての「ツカミ」の道具。会話のきっかけを作る大切な共通点なのです。
アメリカに来てしばらく経ちます。シカゴの空港で、I-20に初めてハンコを押してもらったのは、もう一昨日、昨日の話ではありません。けれど今でも日本の友達に、「もう英語ペラペラでしょう?」と言われることが恐ろしいです。なぜならば、彼らのイメージするペラペラ=ネイティブ。私は生粋の日本人なので、発音面でも、咄嗟に組み立てる文法面でも、まだまだ至らぬ点だらけです。けれどそんなことは大して重要じゃない。言葉をたくみに操れる=コミュニケーション能力が磨かれる、であって、必ずしも完全なる文法かつ発音でコミュニケーションをとることではない。今ある材料でいかに自分の気持ちを正確に伝えるか。相手を楽しませるか。親しみを持ってもらえるか。それが私の考えるべきこと。だから発音や文法を気にしてその練習をしないことは、本当にもったいないこと。そのことに気がついてから、私の英語でのコミュニケーション能力は少なからず伸びたように思います。
![]()
私の語学習得になくてはならなかったもの、それは優しい人々です。日本にいたころ、私は他の国から来た人たちが一生懸命努力しながら話している時に、今こちらの人々が私の話に精一杯耳を傾けてくれるように熱心に彼らに聞き入っただろうか?と恥じ入る思いがしています。つたない言葉を理解すること、それは普通のコミュニケーションより時間と労力を要します。けれどそれをまったく苦にせず、私を理解しようとしてくれるたくさんの人たちのおかげで、私は少しずつ少しずつ、英語に自分の言霊をこめることが出来るようになってきたように思います。
![]()
最初に私の殻を破るお手伝いをしてくれた人たち、それは私の大切なメジャーの友達ふたりです。イタリア育ちのロクサナという女の子と、ご両親がフィリピン人のジェイソンという男の子。去年の秋、授業初日にたまたまロクサナと隣に座ったのが縁で、二人とよく授業で顔を合わせるようになりました。二人はディスカッションで詰まってしまっている私を見ると、よく助け舟を出してくれ、授業で分からないことがあっても面倒なそぶりもみせず、むしろ熱心に説明してくれました。
彼らのおかげで怖くなくなったこと、それは質問をすることです。それは恥でもなんでもないということ。それよりも知らないということが恥なのだということ。彼らにはたくさんの言葉、アメリカ、イタリア、フィリピンの文化、作品を作る技術、たくさんのことを教わりました。そしてありがたいことに、今は私が彼らを、技術面や創作面で助けられることもあります。それによって、私はただ与えられているだけなのだという重荷がなくなり、お互いに成長できる、いい友情関係を築けていると思います。
![]()
もうひとつ、私が英語を話すのが大好きになった場所があります。それはインターン先のオフィスです。今学期は忙しいので、なかなかヘルプに行くことが出来ませんが、オフィスは私にとって、学校で一番居心地のいい場所です。私は今、Center ARTESという、小学児童への芸術普及活動を行っているオフィスで働いています。そこでの私のボス、デイビッドはメキシコ出身で、彼自身も日本への留学経験がある親日家なので、私が日本語を教え、彼は英語、アメリカとメキシコの文化、そしてオフィス業務を私に教えてくれています。
彼は私にいろいろなアメリカ、メキシコを見せたいと言ってくれて、業務時間外も一緒にいろいろなところに出かける親友です。夏休みにはオフィスのみんなで、メキシコ旅行にも出かけました。他のオフィスのメンバーも、生粋のサンマルコス人の子もいますが、ご両親がベトナム出身だったり、自分自身が台湾からの留学生だったり、中国で英語を教えていた人だったりするので、最近は週末に、みんなでお気に入りのエスニック料理レストランへ出かけたりしています。そういうとき、昔ならば私英語話せないし・・・と萎縮していた私でしたが、今は私のままでいればいいのだ、と思っています。判らないことは聞けばいい。彼らも私を嫌っていない。そして何より一緒にいると心地よい仲間。これ以上、何を心配することがある?そう思うのです。
![]()
いまだに英語には悩まされることがたくさんあります。一対一では満足いくコミュニケーションが取れても、大勢のディスカッションでは、頭が一度にたくさんの情報を処理しきれずに、一言も話せないなんて情けないことも時々あります。特に朝一番の授業で頭が半分寝ているときなんか最悪です。何を話しているのか聞き取れずに、聞きなおすことも時々あります。でもそれって、日本語でもあることではないでしょうか?そういう時、私たちは躊躇なく聞きなおしていると思うのです。正しい理解のために。正しいコミュニケーションのために。英語は、確実に私という人間を表す上でのひとつの選択肢になり、私の身体にしっかりと組み込まれ始めている。これは素晴らしいことです。自分を表せる道具は多いほうがいい。私はそう思うのです。