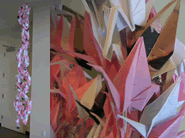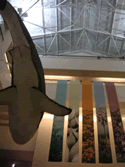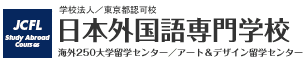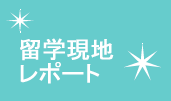No.5
アメリカの大学での勉強の仕方
気がついてみると、アメリカで大学生になってもうずいぶんな年月が経ちます。アメリカの大学では、一般教養科目が必修なので、得意のアートから教科書も開きたくない生物まで、様々なクラスを取ってきましたが、今思うのは、どれひとつとして無駄な授業というものはなかったなぁということです。
私の専攻は芸術です。けれど昔のように、お金持ちが必要とする豪華絢爛な絵が描ければいいという時代は終り、アーティストは創作活動を通じてアクティビストとして活躍する時代になりました。私はこの作品を通して、見る人に何を伝えたいのか。そのアイデアは日々イーゼルに向かってデッサンをしているだけでは、私たちの元へやってきてくれません。ですから、他分野の授業というのは大変刺激的で、私たちをインスパイアしてくれるという意味で、重要な学びの機会のひとつなのです。
先学期の終りに私が作った作品は、卒業単位のために仕方なく受けた生物の実験のクラスの教授にインスパイアされて作ったものです。教授が話してくれたダウン症の原因についての話が非常に興味深く、詳しくお話を聞いているうちにこのアイデアで作品を制作したいと思うようになりました。その後、自分でも勉強をし、DNAの突然変異を自分なりに解釈し、日本人である私を、桜の色であるピンクと白の折鶴で表現しようとDNA二重螺旋を作りました。大切な友達の写真も折鶴にし、私の今まで持っていた“私”に、素晴らしい変異を起こしてくれた要素としてところどころに織り込みました。なかなか手ごろな針金が見つからず、なかなか思った形にすることは出来なかったのですが、私にいつもいい影響をあたえ続けてくれている同志たちに、感謝の気持ちを込めて作れたことにはとても満足をしています。
![]()
また、教授やクラスメイトにアドバイスを求めることは、私にとって最大の学びの機会です。アートに完璧はありません。そう私は思っています。少なくとも私はまだまだ未熟者ですから、学ぶことばかりです。謙虚な気持ちでいれば、教授も友達も親身になってアドバイスをくれます。それにきちんと耳を傾けて、常に向上心を忘れないこと。それは、きっとどんな分野の勉強に関しても、共通しているアイデアなのではないでしょうか。
そしてそのためにも、恐れずに質問をすること。分からないことは聞くに限ります。それは私たちにとって最大の利益なのですから。そして議論の仕方を覚えること。議論というのはお互いを高めるためにするものであって、相手のプライドを傷つけるためにするものではありません。思いやりを持って、相手の意見を尊重し、学びあうこと。それがきっと、アメリカの大学での勉強のコツなのではないかと私は思っています。
来学期は、私にとって大学生活最後の学期になります。正直、もっと学生でいたいと思うこともあります。それだけ私の今いる環境は、制作に適しているということです。けれど集大成として、きちんと何かを作り上げたいと思っています。大切な友達や教授のアドバイスに、様々なことを学びながら。
 |
 |
|
| San Diegoのダウンタウンにある、Balboa Parkで行われたクリスマスイベントに行ってきました。様々な国の料理が並ぶ屋台と、綺麗なイルミネーションで、クリスマス気分を満喫してきました。 | このもみの木は生木なんだそうです。おおきくてとても綺麗なツリーでした。 |